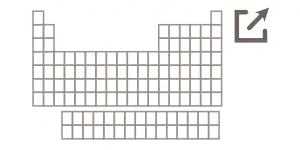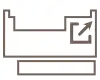仕事の取り出し
これまでは熱機関への熱の出入りに伴って,外界にどれだけの仕事を与えることができるかという点について,熱の効率という観点から議論を行いました。しかし,もともと熱機関は外部(外界)に仕事をするための装置ですから,ある状態の系があったとき,その系からいったいどれくらいの仕事 $\overline{w}$ を取り出すことができるのかというのは重大な関心事です。本節では取り出すことができる仕事という観点から新しい系の状態量を導入します。
エントロピーの定義でもある $\diff S = \dfrac{\delta q_\mathrm{rev}}{T}$ を変形した $\delta q_\mathrm{rev} = T\,\diff S$ の意味するところは,外界から可逆的に熱量 $q_\mathrm{rev}$ が任意の系に与えられたとき,その系の状態に $T\,\diff S$ だけの変化がもたらされるということです。温度 $T$ は熱量が与えられる瞬間の値であり,等温過程でなくても,この関係は過程の経路各点で成立します。断熱系では仮に系に同じエネルギーに相当する仕事を準静的に与えたとしても $T\,\diff S = 0$ です。内部エネルギー $U$ の観点からは,熱で入るか仕事で入るかに依らず,入ってしまえば同じ内部エネルギー(の一部)に組み込まれてしまうわけですが,実はエントロピー $S$ の観点で見れば,熱で入ったか,仕事で入ったかには大きな状態の違いがあるということになります。
第一法則より,気体の体積変化のみを仕事とする準静的過程では以下が成り立ちます。
式\eqref{tspv}は気体の体積変化以外の外界へなす仕事は考えていませんが,体積変化以外の外界への仕事が存在するのであれば,これを $\delta\overline{w}$ として,式\eqref{tspv}を一般化することができます。
ここで言う「体積変化以外の外界への仕事 $\delta\overline{w}$」とは広義の仕事のことで,電気的な仕事や化学エネルギーによる仕事も含まれますし,さらに,気体の体積変化による仕事であっても,外界の圧力と一致するための体積変化ではない,例えばピストンを動かして荷物を移動させるといった仕事は含めることにします。要は,「考えている系からどれくらいの役に立つ仕事が取り出せるのか,その原理的限界が知りたい。ただし,外界の圧力に対応するための気体の体積変化は私たちが欲しい仕事ではないから除外する(別途 $-p\,\diff V$ 部分で表す)」といったことを考えたいわけです。
ヘルムホルツエネルギー
式\eqref{gtspv}において,定温定積での準静的過程を想定します。このような条件では,体積変化を通じた仕事は除外され,外界に取り出せる仕事は主に電気的・化学的などの形でなされることになります。例えば,化学電池のように,体積変化をほとんど伴わず,定温条件下で電気的な仕事を外部に与えるような状況が該当します。
$U$,$T$,$S$ はいずれも状態量ですので,式\eqref{helmde}は,系が外界に準静的に仕事 $\delta\overline{w}$($>0$,系にとっては $w<0$)をなせば,系の状態が $\diff(U-TS)$ で表される分だけ変化(減少)するということを示しています。もうこれ以上 $U-TS$ を減少させることができない(つまり系から取り出せる最大限のエネルギーをすでに外部に与えた)とき,これ以上,系が外界に仕事 $\delta\overline{w}$ をなすことができません。すなわち,最初に系が持っていた $U-TS$ というのは,その時点で系がなすことができる仕事の最大値ということになります。
そこで,この $U-TS$ を新たな状態量 $F$ として定義し,ヘルムホルツエネルギー(Helmholtz energy)と呼ぶことにします。
ヘルムホルツエネルギー $F$ は温度 $T$ における定積変化において系から取り出すことができる仕事の最大値です。エネルギーとしては $U$ だけ持っているにも関わらず,そのうち $TS$ 分は仕事をなすという意味では使い物にならないということです。$TS$ はある温度でのエントロピーに比例する,構成粒子の熱運動によって系内に保持されていて,外部には有効な仕事として取り出せないエネルギーであり,束縛エネルギーと呼ばれます。
摩擦や散逸を伴う現実の過程では,仕事は不可逆になされます。その場合は,$\overline{w}<-\Delta F$ となり,$F$ の減少の割にはあまり仕事がなされない(系の $F$ が無駄に減少する)ということになります。
ギブズエネルギー
次に式\eqref{gtspv}において,定温定圧での準静的過程を考えます。
式\eqref{gibbsde}は,系が外界に定温定圧で準静的に仕事 $\delta\overline{w}$($>0$)をなせば,系の状態が $\diff(H-TS)$ で表される分だけ変化(減少)するということを示しています。そこで,この $H-TS$ を新たな状態量 $G$ として定義し,ギブズエネルギー(Gibbs energy)と呼ぶことにします。
ギブズエネルギー $G$ は温度 $T$ における定圧変化において,系から取り出すことができる仕事の最大値です。現実の多くの相転移,化学反応などの物理・化学過程は定圧条件下で観測されるため,定積条件に基づくヘルムホルツエネルギーよりも,定圧条件で成立するギブズエネルギーが実用上重要な役割を果たすことが多いです。ヘルムホルツエネルギーの場合と同様,仕事が不可逆の場合は $\overline{w}<-\Delta G$ となります。
ギブズエネルギーは,外部への仕事だけではなく,系内部で化学反応や相転移がどの方向に進行するかを決める状態量でもあります。特に化学反応においては,反応物と生成物のギブズエネルギーの差が反応が進む方向を決定し,反応はギブズエネルギーが減少する方向に進み,平衡状態では,反応が進行する駆動力が失われ,ギブズエネルギーが極小となるため,その変化はゼロ($\diff G = 0$)になります。速習編 > 反応の自発性を参照してください。