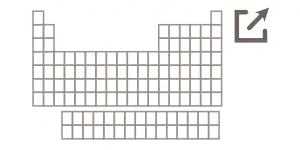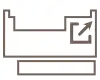溶媒に依存した酸・塩基
酸の英語表記である acid という言葉は,もともとは「すっぱい」(ラテン語の acidus)という意味で使われていたようです。「すっぱい」は漢字で書くと「酸っぱい」ですから日本語で見ても,酸という語には「すっぱい」の意味があったことが分かります。たしかにレモンや食酢のように酸っぱい食品は(現代の私たちが使う意味での)酸性のものが多いですから,酸っぱいものが酸であるという分類は,あながち間違いではありません。
塩基(base)については「石鹸のようにぬめぬめした」ものを塩基と呼んでいたようです。代表的な塩基である水酸化ナトリウム $\ce{NaOH}$ という物質自体は別にぬめぬめしていませんが,$\ce{NaOH}$ 水溶液に触れるとたしかに指がぬめぬめします。英語表記の base は base of salt の略で,「塩の基」という意味です。私たちは塩(えん)を作るには酸と塩基の中和が必要であることを知っているので,その一方だけを「塩の基」と呼ぶことに不思議な感じがしますが,歴史的な物質の捉え方が,表現として現代にまで残った結果だろうと思います。
プロトン $\ce{H+}$ と水酸化物イオン $\ce{OH-}$ に基づく定義
酸っぱいとか,触るとぬめぬめするというのは,味覚や触覚という私たちの感覚に頼っているため,化学的な立場で物質を分類する方法としては適切ではありません。アレニウス(Arrhenius)は酸と塩基を次のように定義しました(1887 年)。
酸とは,水中で水素イオン $\ce{H+}$ を放出する物質である。塩基とは,水中で水酸化物イオン $\ce{OH-}$ を放出する物質である。
はじめにで紹介したように,水素イオンは(化学業界では)プロトンと呼ぶのでした。アレニウスの定義では,もはや味覚に頼る必要はありません。酸っぱくなくても,水中でプロトンを放出すれば酸ですので,アレニウスの定義を採用することで,塩酸や硫酸などの酸っぱくない物質を酸と分類することができるようになり,物質の分類としては一歩前進です。この定義による酸・塩基をアレニウス酸とかアレニウス塩基と呼ぶことがあります。
しかしアレニウスによる定義には明らかな欠点があります。一つは,アンモニア $\ce{NH3}$ のような基本的な物質であっても,この定義では塩基と分類できないことです。アンモニア水は塩基性で,溶液中には $\ce{OH-}$ がたくさん存在していますが,これはアンモニア分子から生じたものではなく,水分子から生じたものです。
そしてもう一つは,わざわざ「水中で」と制約をつけていることです。なぜ水中でなくてはならないのでしょうか。世の中には水以外の溶媒となる物質はたくさんあります。にもかかわらず,水の中でだけ酸が存在すると考えることは合理的でしょうか。水は最も身近で基本的な溶媒であることは確かですが,物質の統一的理解という観点からは,水を特別視する理由はないように思えます。例えば,硫酸水溶液は酸であるけれども,硫酸のエタノール溶液を酸として分類できないことは,統一した物質の理解として正しい方向性なのでしょうか。
溶媒の自己解離に基づく定義
水中という制限をなくした,アレニウスの定義の改良版とも言える定義があり,それは溶媒の自己解離に基づく酸と塩基の定義です。
ある溶媒系で,溶媒の自己解離により生じるカチオンを増やすものが酸であり,アニオンを増やすものが塩基である。
カチオンとアニオンはそれぞれ,陽イオン(cation)と陰イオン(anion)のことです。だったらそう言えばいいのにと思うかもしれませんが,化学の現場ではこちらの表現が多用されます。この定義はアレニウスの定義よりも表現が分かりにくいので,水を例に,具体的に考えてみましょう。水分子 $\ce{H2O}$ は次式のように自らが解離(電離)して,オキソニウムイオン(ヒドロニウムイオン,$\ce{H3O+}$)と水酸化物イオン $\ce{OH-}$ が生じます。
この自己解離は純粋な水の中でも起こっていて,どのくらいの解離が起こっているかは温度によっても変化しますが,水のイオン積で表されるのでした。カチオンを増やすものが酸ということですので,溶媒が水の場合 $\ce{H3O+}$ を増やすもの,すなわち $\ce{H+}$ を放出するものが酸であり,$\ce{OH-}$ を増やすものが塩基と定義されます。例えば,塩化水素 $\ce{HCl}$ は水中で $\ce{H3O+}$ を増やすので,塩化水素は酸であると考えます。これだけを見るとアレニウスの定義と同じで,この定義のメリットを感じられません。
では,次にアンモニアについて考えてみましょう。アンモニアは沸点が $-33\oC$ ですので,液化しやすく,溶媒として用いられます。アンモニアの自己解離とは,次式のように解離して $\ce{NH4+}$ と $\ce{NH2-}$ が生じることです。
$\ce{sol}$ は溶媒和しているという意味で,ここでは(あまりこういう言い方はしませんが)アンモニア和していることを表しています。この場合,アンモニア中でカチオンである $\ce{NH4+}$ を増やす物質が酸,アニオンである $\ce{NH2-}$ を増やす物質が塩基と定義されます。具体的には,塩化アンモニウム $\ce{NH4Cl}$ はアンモニア溶媒中で電離して $\ce{NH4+}$ を増やしますので酸です。塩化水素もアンモニア中で塩化アンモニウム $\ce{NH4Cl}$ となり,やはり $\ce{NH4+}$ を増やしますので酸です。一方,ナトリウムアミド $\ce{NaNH2}$ は,アンモニア中で $\ce{NH2-}$ を増やしますので塩基です。
このように酸と塩基を定義することは合理的なのでしょうか。中和は酸と塩基が関係する代表的な反応です。アンモニア溶媒に酸と分類された $\ce{NH4Cl}$ と塩基と分類された $\ce{NaNH2}$ を加えてみましょう。
酸と塩基から,塩($\ce{NaCl}$)と溶媒($\ce{NH3}$)が生成しました。これは中和反応そのものです。このように,溶媒の自己解離に基づく酸・塩基の定義は,たしかにアレニウスの定義と比べて,より広範に酸塩基の概念を適用することができるようになります。しかし,この定義は溶媒の存在を前提としているため,まだまだ概念の一般化という意味で成熟していません。溶媒の存在を仮定せずとも酸・塩基を定義できるのが,次節で紹介するブレンステッド(Brønsted)とローリー(Lowry)による定義です。