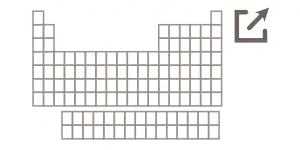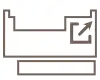用語の解説 1
議論を円滑に進めるために,いくつかの用語を定義し,その用語が示す適用範囲を予め約束しておきます。実際に新用語を使うタイミングで説明してもよいのですが,学習の最初の段階で新しい用語が次々と出てきて,これらを都度説明しては議論の見通しが悪くなってしまいます。主だったものをここでまとめ,それ以外は登場の都度説明します。ただし説明の都合で,例えば「熱」「仕事」など,まだ本編では定義していない用語を使う場合があります。その場合は速習編や高校理科編で定義済みと考えるか,あるいはとりあえず常識的な意味でとらえておいて,後に定義されてから振り返って確認していただければと思います。
系と外界
熱力学では着目して観測の対象となる部分を系(system),系以外のすべての部分を外界(surroundings)あるいは外部系と呼んで,世界を系と外界に二分します。例えば,密閉容器に入った気体について議論するのであれば,容器の内部が系で,容器を含むそれ以外のすべてが外界です。系は壁のようなもので実際に区切られている必要はなく,認識として境界が定まっていればよいです。例えば,ビーカーに液体の水を入れたとき,空気に接している水面は具体的な壁で区切られているわけではありませんが,液体の水の部分のみを系として考えても構いません。
熱力学の適用範囲とも関係しますが,系は少なくとも観測の時間スケールで物理量が一定値とみなせる程度に巨視的であるとします。分子が一つだけとか二つだけしか含まれない程の小さい領域は,(その分子を対象として)熱力学で取り扱える系ではありません。
容器の内部が二つの部屋に壁で区切られていたとしても,両方まとめて着目するのであれば両方を合わせたものを系としてもかまいません。ただし議論の都合上,二つの部屋を別個に考える方が都合がよいのであれば,系 1,系 2のように系を任意に分割した部分系を考えてもよいです。
容器を二つに分ける区切りは実際の壁でなく,仮想的なものでも構いません。例えば液体の水と空気が入った密閉容器の内部を観測の対象とするとき,容器の内部全体を一つの系と考えてもよいし,液体部分と気体部分を系 1,系 2 として部分系に分割し,それらが合わさったものが全体の系(全系)であると考えてもよいです。熱も物質も通さない壁,物質は通さないが熱は通す壁,あるいは半透膜のように特定の物質のみを透過させる壁もあり得ます。あるいは明確な境界がない部分を仮想的な境界として部分系に分割することも許されます。したがって,気体が入った壁のない密閉容器であっても,必要に応じて系を仮想的に分割して部分系を考えることができます。
外界との間で物質が出入りできる系を開いた系(open system,または開放系),物質の出入りが許されない系を閉じた系(closed system)と言います。蓋のないビーカーは,物質が自由に出入りできるので開いた系であり,密閉容器は閉じた系です。閉じた系であってもエネルギーの出入りや体積の変化に制限はないので,密閉されたピストン付き容器の内部も閉じた系です。
閉じた系でかつエネルギーの出入りもできず,さらに電場や磁場などの外場を介した外界とのやり取りも一切できない系を孤立系(isolated system)と言います。孤立系を考えた場合は外界の存在は考える必要がありません。一方,熱だけに着目し,熱が出入りできない系を断熱系(adiabatic system)と言います。断熱系は熱以外のエネルギーの出入りや,外場の影響については定めていないので,それらの条件は別途指定する必要があります。この定義から,孤立系は断熱系の特別な場合(孤立系 $\subset$ 断熱系)であることがわかります。ただし本講義では,特に言及しない限り外場は存在しないものとし,その他のエネルギーの出入りについてのみ都度指定することにします。
系全体の均一性に着目して,全体が均一である均一系(homogeneous system)と,不均一である不均一系(heterogeneous system)に分類することもできます。ここでの均一とは,系のどの巨視的な一部分を切り出しても,切り出した形と体積が等しければ,他の部分と巨視的には区別がつかないことをいいます。窒素と酸素の気体を密閉容器内で混合すると,混合直後は不均一系(切り出す場所によって窒素と酸素の含まれる割合が異なる)ですが,時間が経てば均一系になります。液体の水と空気を入れた密閉容器の内部全体は不均一系ですが,液体部分と気体部分を別々の部分系に分割すれば,それぞれの部分系は均一系です。
熱浴と熱源
議論を簡潔にするために特別な外界を考えることがあります。熱浴は温度が一定の恒温槽のことで,系のスケールに対して十分に大きく,系に熱を与えても自身の温度が変化せずに保たれる外界のことです。定温過程を観察したいときに系(もちろん断熱系ではダメです)を恒温槽にまるごと入れるような使い方をします。
熱源も系に対して十分大きく,温度が一定に保たれている外界です。意味するところは熱浴に近いのですが,異なる二つの温度の熱源を用意して一方の熱源から他方の熱源に熱を移すといった際の考察に用います。系をまるごとドボンと浸けるような使い方ではないので「浴」ではなく「源」としています。
熱浴と熱源は言葉のニュアンスの違いですので,特に区別せずに用いることもあります。
熱平衡状態と熱平衡
熱力学は,孤立系を長い時間放置すると,やがて系が一定の状態に落ち着き,その後は巨視的な時間変化をしなくなるという私たちの経験から得た知見を,自然の摂理(すなわち事実)として証明することなしに受け入れます。この落ち着いた状態を熱平衡状態(thermal equilibrium state)あるいは単に平衡状態(equilibrium state)と言います。孤立系ではなくても,外界が系に対して十分大きく,圧力や温度などの系に影響を及ぼす因子が一定に保たれているとみなせるのであれば,系はやがて一定の状態に落ち着くので熱平衡状態が達成されます。例えば,恒温槽に入れた(断熱ではない)容積一定の密閉容器の内部を系とするとき,系はエネルギーの出入りが許されるので孤立系ではありませんが,巨視的な時間変化をしない状態に落ち着いたのであれば,この系は熱平衡状態にあります。系を部分系に分割して考えた場合,全系が平衡状態にあるのであれば,各部分系も平衡状態にあるといえます。
二つの系が,熱をやり取りできる状態で接したとしても,それぞれの系が巨視的な時間変化をせず,かつ二つの系の間にエネルギーや物質の巨視的な流れがないとき,二つの系は熱平衡であると言います。上述した,恒温槽に入れた容積一定の密閉容器内部の系は,外界である恒温槽と熱平衡にあり,かつ系自身が熱平衡状態にあると言えます。
準静的過程
ある熱平衡状態があり,この平衡状態を形成している条件をほんの僅かだけ変えることで,元の状態からほんの僅かだけ変化した別の平衡状態が生じるとします。この「ほんの僅か」をできるだけ小さく,すなわちできるだけゆっくりと条件を変化させる極限を考えることで,変化の過程のどの瞬間をとっても系が熱平衡状態であるという特別な状況を考えることができ,これを準静的過程(quasi-static process)と言います。
そもそも熱平衡状態は時間変化しないとして定義されているので,準静的過程は熱平衡状態が維持されているのに系が変化するという矛盾した設定です。しかし,本来,熱力学で扱えない「変化」を扱えるようにする仕組みであり,着目する系のスケールに応じた十分な実験的精度で擬似的に実現することは原理的に可能ですので,しばしば議論に登場します。
可逆過程と不可逆過程
系がある変化をしたとき,一般には外界の状態にも変化が生じます。このあと,原理的に系と外界の両方を元の状態に戻すことができるのであれば,その変化の過程を可逆過程(reversible process)といい,可逆過程ではない変化の過程を不可逆過程(irreversible process)と言います。
可逆過程は系と外界の両方が元に戻ればよいので,変化させる過程と,それを元に戻す過程は(戻りさえすれば)異なる経路をたどってもかまいません。系だけが元に戻り,その際に外界は元には戻らず,何らかの影響が残ってしまう過程は可逆過程ではありません。準静的過程は常に平衡状態が成り立つとみなすことができるというのが定義ですから,準静的過程はたどった変化の経路を逆行させることができます。よって準静的過程ならば可逆過程です。
一方,可逆過程が常に準静的過程であるとは限りません。ただし,熱力学の議論の範疇では,可逆だが準静的ではないという状況はつくりにくく,可逆性を得るためには準静的でなくてはならないので,準静的過程を可逆過程と同一視しても議論に影響がない場合が多いです。
- 準静的過程 $\subset$ 可逆過程
可逆過程だからといって準静的過程であるとは限らないが,熱力学で想定する範疇では,準静的過程 $=$ 可逆過程とみなして問題ない場合が多い。