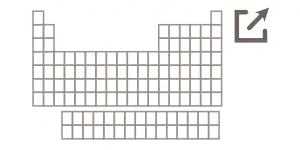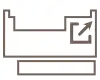用語の解説 2
状態量と状態関数
系が熱平衡状態であるときに,その平衡状態に応じてただ一つに定まる物理量を状態量(state quantity)と言います。系の体積 $V$ は状態量ですが,等しい平衡状態であっても系の形は異なる場合があるので,系の表面積は状態量ではありません。
一方,逆は成り立たず,二つの系のある状態量が等しいからと言って,その二つの系が等しい平衡状態にあるとは限りません。例えば,温度 $T$ は状態量の一つですが,ピストン付き容器に水を入れて大気圧下で準静的に加熱すると,$100\oC$ で液体の水と水蒸気の二つの相が生じ,加熱する時間によって $100\oC$ が保たれたまま系の体積 $V$ や液相と気相の比率は変わります。したがって,温度が等しくても異なる平衡状態は存在するので,温度のみが定まっていたとしても系の平衡状態を定めたことにはなりません。
状態量一つでは平衡状態を定めることができないとしても,いくつかの状態量を組み合わせることで系の平衡状態をただ一つに定めることができるだろうと考え,この状態量のセットを見つけ,それらの状態量の間の関係を明らかにすることが熱力学の重要な目標の一つとなります。状態量の間の関係を記述する関数を状態関数(state function)といい,平衡状態を定めるのに必要な状態量は状態変数(state variable)と呼ばれます。通常,必要な状態変数の数は最小限にしたいので,状態変数となる状態量は一般に互いに独立(他の状態変数を固定したまま,一つの状態変数を変化させることができる)となりますが,状態変数を状態関数に代入することにより定まる状態量は従属(他の状態変数と状態関数により定まる状態量の両方を固定したまま,一つの状態変数を変化させることはできない)です。ただし,どの状態量を状態変数(独立変数)として選ぶかは任意で,どの状態量であっても,セットの取り方によって独立にも従属にもなれるので,状態量,状態変数,状態関数の用語を厳密に区別しないで用いる場合もあります。
状態関数を状態変数によって表す数式を状態方程式(equation of state)と言います。状態量が定まっていることが前提ですので,熱平衡状態に対してのみ状態方程式が適用できます。
状態量 $X$ は,その定義により始状態と終状態の平衡状態でそれぞれただ一つに定まります。これらをそれぞれ $X_\mathrm{i}$,$X_\mathrm{f}$ とすると,$X$ の変化量 $\Delta X$ は始状態と終状態によってのみ決まり,$X_\mathrm{f}$ に至る経路には依存しないことになります。
状態関数 $X$ が状態変数 $A$,$B$,$C$ からなる $X(A,B,C)$ であるとします。状態関数の微小変化 $\diff X$ は,$X$ の状態変数を用いて,全微分の形で書くことができます。
この式の意味するところは,状態変数 $A$,$B$,$C$ が少しだけ変化したときの $X$ の微小変化 $\diff X$ は,$B$ と $C$ を固定して $A$ だけを変化させたときの変化率(偏微分係数)と $A$ の微小変化量 $\diff A$ の積と,$C$ と $A$ を固定して $B$ だけを変化させたときの変化率と $B$ の微小変化量 $\diff B$ の積と,$A$ と $B$ を固定して $C$ だけを変化させたときの変化率と $C$ の微小変化量 $\diff C$ の積の和で表されるというものです。簡単に言うと $A$,$B$,$C$ それぞれの方向の変化を足し合わせたものが全体の変化ということです。詳しくは,補足 > 偏微分と全微分にて解説しています。
状態関数が経路によらないのに対して,最終的な系の状態が等しい場合でも,その状態に至る道筋によって変化しうる物理量を経路関数(path function)と言います。熱と仕事はどちらもエネルギーの一形態であることを学びました。最終的に系が得たエネルギーが分かっても,それが熱と仕事のどちらで与えられたものか,あるいは両方だとして,それぞれの割合はどのくらいかは途中過程を見てみないと分かりません。よって熱量 $q$ や仕事 $w$ は経路関数です。
非平衡状態では,系の状態は定まっていないので,熱力学的な意味では一般に状態量も定まらないと考えるべきです。ただし例えば,容積一定の密閉容器の内部を系とするのであれば,系が平衡状態か非平衡状態かに関わらず,系の体積は定まっていると考えることができますので,非平衡状態ではすべての物理量が定まらないという意味ではありません。
状態量の示量性と示強性
物理量には系の大きさ(量)に依存するものと依存しないものがあります。系を半分に分割して二つの部分系にしたとき,各部分系の体積は分割前の体積の半分(当たり前!)です。一方,系の温度が $20\oC$ だったからと言って,部分系の温度が半分の $10\oC$ になるということはありません。系の大きさに比例する物理量を示量性(extensive)の物理量,系の大きさに依存しない物理量の示強性(intensive)の物理量と言います。特に均一系が熱平衡状態にあるときは,状態量を示量性状態量や示強性状態量と呼んで区別します。
例えば,圧力 $p$ の平衡状態にある気体を均一系とし,系を(圧縮や膨張なしに)いくつかに分割した部分系を考えます。分割後の各部分系の圧力は元の系の圧力 $p$ と変わらないので,圧力 $p$ は示強性状態量(示強変数)です。一方,系に含まれる粒子数 $N$ は,部分系の体積に比例しますので,粒子数 $N$ は示量性状態量(示量変数)です。
均一系において示量性状態量であっても,不均一系であれば,いくつかの等しい体積に分割したうちの,いずれか一つの部分系の状態量を分割数倍しても,全体の系の状態量になるとは限りません。例えば気液平衡にある系を等体積で分割して,液体部分のみを含むある部分系の粒子数を分割数倍しても,気体部分については考慮されないので全体の粒子数 $N$ には一致しません。よってこの場合の粒子数 $N$ は示量性状態量ではありません。ただし,不均一系を分割して,各部分系を均一系にすることができるのであれば,各部分系の中の粒子数は示量性状態量ということになります。また,分割した各部分系の粒子数 $n_i$ を(単純に分割数倍するのではなく)すべて足し合わせて $\sum_in_i$ とすれば分割前の粒子数 $N$ と等しくなりますので,不均一系では示量性ではなくても加成性は残ります。
相転移
温度や圧力などの条件の変化に伴い,物質が三態の変化のように異なる状態(相)へと変化する現象を相転移(phase transition)と言います。水が加熱によって液体から気体へと変化する現象は典型的ですが,鉄が加熱によって強磁性から常磁性へと変化する現象も相転移の例です。相転移は物理的な性質の急激な変化として現れ,それぞれの相では物質の構造や性質が大きく異なります。
相転移が起こるとき,温度や圧力が変化していないにもかかわらず,状態量が不連続に変化することがあり,このような相転移を一次相転移(first-order phase transition)と呼びます。水の沸騰や氷の融解は典型的な一次相転移です。
一方,超伝導や強磁性の転移点のように,状態量自体は連続であるものの,状態関数の二階導関数に関連する物理量(例えば熱容量など)が不連続となる相転移もあり,これは二次相転移(second-order phase transition)あるいは連続相転移と呼ばれます。
相転移の際には,ある温度や圧力のもとで複数の相(例えば液体と気体)が共存する領域が現れます。このような状態では,温度や圧力などの示強性状態量が等しくても,相の構成比によって示量性状態量が異なり,同じ示強性状態量でも平衡状態が一意に定まらないという特徴があります。したがって,このような領域では状態関数の扱いに注意が必要です。
理想気体
状態方程式 $pV=nRT$ が厳密に成り立つ気体を理想気体(ideal gas)と言います。$pV=nRT$ が成り立つためには気体分子の体積が系の体積に対して無視できるほどに小さく,気体分子間の相互作用が無視できるほどに小さい必要がありますので,こちらの条件を理想気体の定義として先に出し,理想気体であれば $pV=nRT$ に従う,と主従を逆に説明することもできますが,前者の立場をとる場合が多いように思います。現実に存在する気体は実在気体(real gas)といい,実在気体は希薄になるほど理想気体の振る舞いに漸近します。
理想気体は従うべき状態方程式を規定しているだけですので,異なる複数種類の理想気体からなる混合気体を想定することもできます。また,理想気体が単原子分子である必要もなく,二原子分子や多原子分子のような分子構造を持つ理想気体を想定しても構いません。この場合,いずれの理想気体も状態方程式 $pV=nRT$ には従いますが,その他の性質は分子構造に依存して異なる場合があります。
気体定数 $R$
理想気体の状態方程式 $pV=nRT$ の左辺の次元はエネルギーの次元に等しくなります($\mathrm{Nm^{-2}\cdot m^3 = kg\, m^2\, s^{-2}}$)。$n=1\unit{mol}$ のとき,$RT$ は $1\unit{mol}$ あたりのエネルギーを表します。つまり気体定数 $R$ は,$1\unit{mol}$ あたりのエネルギーを温度 $T$ で割ったものとなり,$1\unit{mol}$ あたり,$1\unit{K}$ あたりのエネルギーを表しています。$1\unit{mol}$ の分子からなる理想気体の温度が $1\unit{K}$ 上昇するとき,理想気体のエネルギーは $R$ だけ上昇するということです。1 分子あたり,$1\unit{K}$ あたりのエネルギーはボルツマン定数 $\kB$ で表され,$R=\NA\kB$ です。