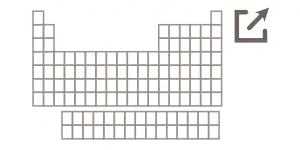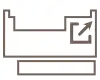本編・はじめに
速習編と高校理科編では,化学の学習に必要な熱力学の一番土台の部分について学習しました。本編では,改めて熱力学の基礎から順に学習します。速習編・高校理科編の内容を適宜復習しながら進めますが,基本的な事項については既習として話を進めます。
さて,改めて熱力学とはどのような学問でしょうか。熱力学を適用する学問分野によって切り口が違うので唯一の定義を与えることは難しいのですが,ここでは化学の視点で以下のように熱力学を位置づけることにします。
微小な存在の集合体に由来する,巨視的に時間変化しない状態を,巨視的な立場で扱う学問を熱力学(thermodynamics)という。特に,物質の熱的現象に関わる学問であることを強調する場合には化学熱力学と称する。
化学は通常,原子や分子を対象としますので,ここでの「微小な存在」は原子や分子のサイズをイメージすればよいでしょう。集合体のスケールについては,化学ではアボガドロ数個ほど($10^{23}$ 個程度)が基本となり,この場合は特に心配なく十分な数からなる集合体を扱っていると考えてよいのですが,最近の化学では 1 分子とか,数原子といった少ない個数を直接扱うことも技術的に可能になってきました。その場合,どこかに集合体として巨視的にみることが適当ではない(すなわち熱力学では扱えない)境界線があるはずです。
思考実験として例えば,2 本のスティックを使ってスネアドラムでタン・タン・タン・タンと四分音符を刻んでみましょう。個々の音は分離して聞こえます。このときスネアドラムの内部に圧力計を設置すると,圧力計の針は音の刻みに合わせて変動するでしょう。あるいは私たちの鼓膜も音の刻みに合わせて反応しているはずです。これは圧力計や我々の聴覚の時間分解能が,タン・タン・タン・タンという現象の時間スケールよりも優れていることを意味します。次に 2 人で 4 本のスティックで均等に時間をずらして叩くとタタタタと八分音符になりますが,まだ個々の音を認識することは可能でしょう。しかし,スティックの本数をどんどん増やして十六分,三十二分としていくと,やがてダララララ~と激しいドラムロールのような刻みを経て,最終的には(思考実験なので技術的に可能かは別として)個々の音は分離せずに,連続的な音として聞こえるようになるはずです。また,このときの圧力計の針の変動はどんどんと小さくなり,一定値を示したまま動かなくなるはずです。
同じことが,個々の気体分子が容器の壁に衝突した結果として生じる気体の圧力にも言えるでしょう。微視的には個々の分子が壁に衝突するタイミングはバラバラですから,極短時間でみると気体分子が容器の壁に及ぼす力の総和はゆらいで,時々刻々と変化しているはずです。しかし,分子数が極めて多くなると,観測の時間スケールでは力の総和の変動は平均化され一定値とみなせるようになります。ですから,どこに境界線があるかを予め決めるのではなく,逆に「もうこれなら一定値とみなしていいや」と思えるラインから先が熱力学で扱える領域だと理解することにします。
熱力学は,この一定値とみなせる物理量どうしの関係を記述する学問です。したがって微視的には異なる状態であっても,巨視的に等しいのであれば同一の状態とみなしてしまうのが熱力学の約束であり,この「細部を捨てて巨視的視点に立つ」という大胆な作戦により,アボガドロ数個ほどの原子や分子が引き起こす現象であっても,わずか数個のパラメータで系の状態を記述することに成功しているのが熱力学の強みです。
さて,上の定義には「時間変化しない」という表現が含まれています。状態変化や化学反応など,変化は化学の重要な関心事項ですので,時間変化しないという条件は熱力学の適用範囲をかなり制限してしまうように思うかもしれませんし,実際,変化している最中は熱力学の適用外です。しかし,変化する前(の平衡状態)と,変化した後(の平衡状態)は熱力学の対象ですし,変化の過程を適用外にするということは逆に言うと,変化の過程に関わらず,最初と最後は熱力学で決まるという意味でもありますので,これはむしろ強みでさえあります。「途中はいいから,結果だけ教えて」というせっかちな方にも応えてくれるのが熱力学です。
このように,化学変化を考える際にも熱力学は重要な役割を果たしますが,基礎編では化学変化や物質の出入りがあるような場合(開いた系)については扱わず,閉じた系に限定した議論を行うことにします。開いた系の扱いについては概論編での扱いを予定しています。