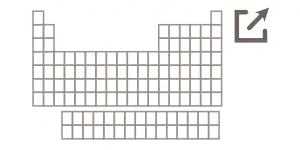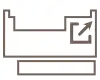熱容量
定積条件では与えられた熱量 $q$ と内部エネルギー変化 $\Delta U$ が一致し,定圧条件では $q$ とエンタルピー変化 $\Delta H$ が一致することを学びました。しかし,この情報のみで系の温度がどのくらい変化するかを知ることはできません。なぜなら,$q$ による内部エネルギーの変化のすべてが系の温度変化に使われているわけではないからです。系を構成する分子の並進運動だけではなく,回転や振動,分子間の相互作用など,内部エネルギーの内訳は多岐にわたるのでした。これらの内訳の割合は物質によって異なるだけではなく,温度,体積,物質量(粒子数)などの状態量にも依存しますので,熱量 $q$ を与えたという情報だけから内部エネルギーの内訳がどう変化したかは分からず,温度変化を知ることもできません。そこで,熱容量(heat capacity)$C$ を以下で約束します。
ある系の温度をある温度から単位温度($1\unit{K}$)だけ高くするのに必要な熱量 $q$ を,その条件での系の熱容量とする。
ここで「その条件での」と制約を加えているのは,上述のように $1\unit{K}$ だけ温度を高くするのに必要な熱量は定積条件や定圧条件などの条件に加え,系の状態に依存するためです。同じ系でも定積条件で $20\oC$,$1\unit{atm}$ の条件で $1\unit{K}$ の温度上昇を行うのと,$50\oC$,$10\unit{atm}$ の条件で $1\unit{K}$ の温度上昇を行うのとでは必要な $q$ が異なるということです。
条件によっても状態によっても異なる熱容量ですが,まずは大きく定積条件と定圧条件での熱容量に分けて考えるのが一般的です。
定積熱容量と定圧熱容量
定積条件での熱容量を定積熱容量といい $C_V$ で表します。定積条件では,与えた熱量 $q$ が内部エネルギー変化 $\Delta U$ と一致するので,$C_V$ は次式で定義されます。
偏微分の形で書きましたが,要は温度を $1\unit{K}$ 変化させるのに必要な熱量( $= U$ の変化量)ということです。実用上は物質 $1\unit{mol}$ あたりの熱容量で表示した方が物質の種類のみに依存し,量に依存しなくなるので便利で,$U$ の代わりにモル内部エネルギー $U_\mathrm{m}$ を偏微分した モル定積熱容量 $\Cvm$ が使われます。一方,定圧条件での熱容量を定圧熱容量といい $C_p$ で表します。定圧条件では与えた熱量 $q$ がエンタルピー変化 $\Delta H$ と一致しますので,$C_p$ は次式で定義されます。
内部エネルギーとエンタルピーの良い対応関係をここでも見ることができます。こちらも実用上はモル定圧熱容量 $\Cpm$ を使うことが多いです。
さて,ある物質の $\Cvm$ と $\Cpm$ はどのような関係にあるでしょうか。定圧条件では温度を上昇させるのに,仕事として使われてしまう分を加味して余分に熱を与えなくてはなりません。したがって,他の条件が等しければ,$\Cvm$ と $\Cpm$ の大小関係は以下となります。
定圧条件であっても温度変化による体積変化が厳密にゼロであれば,式\eqref{cpcv}の両辺はイコールで結ばれますが,理論的な極限を除けばそのような物質は存在しないと思われます。また,水などの異常収縮を示す物質では,温度上昇によって水素結合などのミクロな構造が変化し,体積が減少する温度領域(水であれば $0$ ~ $4\oC$)があります。外界から仕事分のエネルギーを受け取るので,$\Cpm$ の方が $\Cvm$ より小さくなりそうだと考えるかもしれません。しかし,体積の変化が負(異常収縮)の場合でも,その変化は水素結合ネットワークの再編成といったミクロな構造変化を伴います。このような構造変化には,単純な温度上昇以上に内部エネルギーの変化が必要となるため,現実的には $\Cpm$ は $\Cvm$ よりも大きくなります。
単原子分子理想気体の熱容量
通常,熱容量は物質ごとに異なり,個々に実験によって求める必要がありますが,特定の条件を満たせば理論的な熱容量を見積もることができます。理想気体は状態方程式 $pV=nRT$ に従う気体として定義されていますが(本編 > 用語の解説 2),これは分子間の相互作用がないことを意味します。したがって理想気体では系の体積や圧力が変わっても温度が一定であれば内部エネルギーは変化しません。
式\eqref{jouler}はジュールの法則と呼ばれている理想気体限定で成り立つ関係です。(閉じた系では)理想気体の内部エネルギーを変化させることができるのは温度 $T$ だけ,すなわち $U = U(T)$ です。
系の温度に寄与する分子の運動には並進の他に回転や振動もありますが,単原子分子であれば,分子の回転や振動エネルギーを考える必要がなくなります。よって,両方の特徴を備えた単原子分子の理想気体では,熱による内部エネルギー変化は分子の並進運動エネルギーの変化と直結します。高校理科編 > 気体の法則では,分子運動論に基づいて気体分子の平均運動エネルギーが $\frac{3}{2}\kB T$ であると求めました。つまり系の内部エネルギーと温度 $T$ がダイレクトに結びついていることになります。これは 1 分子あたりのエネルギーですので $1\unit{mol}$ あたりでは $\frac{3}{2}RT$ です。すなわち $1\unit{K}$ の温度上昇で $1\unit{mol}$ の単原子分子理想気体の内部エネルギーは $\frac{3}{2}R$ 上昇することになります。よって,単原子分子理想気体ではモル定積熱容量を次式で表すことができます。
では,モル定圧熱容量はどのようになるでしょうか。$H=U+pV$ に $pV=nRT$ を代入します。
式\eqref{cpmj}の右辺第一項は圧力一定で温度を変えたときのモル内部エネルギー変化(つまり体積は変わってもよい)という意味ですが,ジュールの法則より理想気体では体積が変わることによる内部エネルギー変化への寄与はゼロ(そもそも $U_\mathrm{m}$ は $T$ だけの関数)ですので,結局この項は圧力一定であろうと体積一定であろうと同じで $\Cvm$ で表されます。よって式\eqref{cpmj}は次式に変形されます。
式\eqref{mayer}はマイヤーの関係式と呼ばれており理想気体限定で成り立ちます。これにより単原子分子の理想気体の $\Cpm$ が求まります。
多原子理想気体の熱容量
単原子分子理想気体では分子の並進運動(自由度 3)のみを考えればよかったのですが,多原子になると回転運動や振動も考慮する必要があります。統計力学のエネルギー等分配則に基づく知識が必要になりますが,ここでは結果だけを書くと,自由度 1 につき,$\Cvm$ への寄与は $\frac{1}{2}R$ であり,2 原子分子あるいは 3 原子以上であっても直線分子であれば,回転の自由度は 2 ,非直線分子であれば回転の自由度が 3 になります。よって回転運動を考慮した場合の多原子理想気体の $\Cvm$ は以下で表されます。
マイヤーの関係式は理想気体のタイプによらず成り立ちますので,$\Cpm$ についても求めることができます。
実際にはさらに振動の影響を考えなくてはなりませんが,その寄与は並進や回転のように簡単な式で表すことができません。低温においては振動状態の励起は少ないので熱容量に対する寄与は小さく,高温になるほど寄与が大きくなるので,一般に温度が高くなるほど熱容量は値が大きくなります。