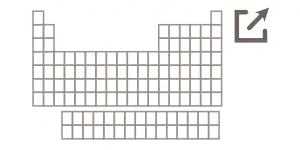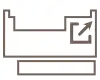熱容量の実際
熱容量が分かれば与えた熱量 $q$ から温度の変化を予測することができるのですが,熱容量は系により異なり,さらに状態によっても異なるとなると,もはや着目する系の熱容量を知ることは都度実験で求めない限り不可能であるように思えますし,厳密にはその通りなのですが,それではあまりにも不便です。実際のところは,ある温度と圧力での熱容量の情報があれば,それに近い条件の範囲では熱容量も近い値を持っているか,あるいは補正式によって近似した熱容量を求めることが可能です。
化学熱力学では物質に着目した系を考えることが多いので,純物質ごとの熱容量が分かると便利です。そこで,色々な純物質の熱容量を代表的な条件のもとで実験で調べておいて,それをデータベースとしてまとめておくという方法がとられています。具体的には標準状態圧力(SSP,速習編 > 標準状態)である $1\unit{bar}$ における熱容量が報告されています。温度は標準状態では定められていませんので,$298.15\unit{K}$ のピンポイントで報告されているもの(物質の種類は多い)もあれば,物質は厳選されていますが複数の温度で報告されているものもあります。
熱容量はその定義から系のサイズに依存しますので示量性ですが,データベースでは $1\unit{mol}$ あたりの熱容量に換算してモル熱容量 $C_\mathrm{m}$ として報告されるのが一般的です。モル熱容量の単位は現在は $\mathrm{J\,K^{-1}mol^{-1}}$ が使われますが,古い文献では $\mathrm{cal\,K^{-1}mol^{-1}}$ で表示されていることもありますので注意が必要です。以下に Thermochemical Data of Pure Substances より引用した純物質の標準状態におけるモル定圧熱容量 $\Cpm^\circ$ の例を示します。
| $T\,/\unit{K}$ | $\ce{He}$ | $\ce{Ne}$ | $\ce{Ar}$ | $\ce{H2}$ | $\ce{N2}$ | $\ce{O2}$ | $\ce{Cl2}$ | $\ce{CO2}$ | $\ce{CS2}$ | $\ce{H2O(g)}$ | $\ce{CH4}$ | $\ce{SF6}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| $298.15$ | $20.786$ | $20.786$ | $20.786$ | $28.836$ | $29.123$ | $29.376$ | $33.942$ | $37.132$ | $45.677$ | $33.590$ | $35.645$ | $96.963$ |
| $300.00$ | $20.786$ | $20.786$ | $20.786$ | $28.849$ | $29.125$ | $29.385$ | $33.972$ | $37.217$ | $45.750$ | $33.596$ | $35.707$ | $97.391$ |
| $400.00$ | $20.786$ | $20.786$ | $20.786$ | $29.182$ | $29.246$ | $30.106$ | $35.273$ | $41.326$ | $49.613$ | $34.261$ | $40.489$ | $116.369$ |
| $500.00$ | $20.786$ | $20.786$ | $20.786$ | $29.260$ | $29.583$ | $31.091$ | $36.080$ | $44.625$ | $52.545$ | $35.230$ | $46.349$ | $128.352$ |
| $600.00$ | $20.786$ | $20.786$ | $20.786$ | $29.326$ | $30.113$ | $32.089$ | $36.588$ | $47.323$ | $54.667$ | $36.322$ | $52.232$ | $136.062$ |
| $700.00$ | $20.786$ | $20.786$ | $20.786$ | $29.442$ | $30.752$ | $32.981$ | $36.927$ | $49.563$ | $56.252$ | $37.494$ | $57.798$ | $141.231$ |
| $800.00$ | $20.786$ | $20.786$ | $20.786$ | $29.625$ | $31.430$ | $33.734$ | $37.165$ | $51.434$ | $57.477$ | $38.723$ | $62.929$ | $144.803$ |
| $900.00$ | $20.786$ | $20.786$ | $20.786$ | $29.880$ | $32.094$ | $34.354$ | $37.341$ | $52.999$ | $58.453$ | $39.988$ | $67.591$ | $147.375$ |
| $1000.00$ | $20.786$ | $20.786$ | $20.786$ | $30.205$ | $32.696$ | $34.870$ | $37.479$ | $54.308$ | $59.245$ | $41.267$ | $71.782$ | $149.271$ |
この表より,単原子分子(貴ガス $\ce{He}$,$\ce{Ne}$,$\ce{Ar}$)はいずれも温度に関わらず,単原子分子理想気体の理論値である $\frac{5}{2}R$ に近い値が報告されています。
前節で紹介した二原子分子理想気体の理論値は $\frac{7}{2}R \approx 29.10\JKmol$ です。室温付近の $\ce{N2}$ がこれに近い値を示していて,理想気体に近いふるまいをしていることが分かります。これが $\ce{O2}$ や $\ce{Cl2}$ になってくると,室温でも理想気体の理論値からの乖離が見られるようになり,少なくとも $1\unit{bar}$ においては分子間の相互作用が無視できないことを示しています。興味深いのは $\ce{H2}$ で,小分子でいかにも理想気体的なふるまいをしそうですが,室温では理論値よりもむしろ小さな値を示しています。二原子分子では並進に加えて回転運動が自由度 2 の $R$ 分だけ熱容量に寄与しますが,$\ce{H2}$ のような軽い原子からなる分子では量子効果が強く現れ,回転準位のエネルギー間隔が大きくなります。そのため,熱エネルギー $\kB T$ が十分でない室温付近では回転準位がほとんど励起されません。前節の熱容量の理論値は(古典)統計力学に基づくものなので,熱エネルギーに対して離散化した回転準位のエネルギー間隔が大きいと,回転運動による $R$ の寄与をまるまる得ることができず,熱容量が小さめになることが予想されます。一般に小分子の方が理想気体に近いふるまいをするように考えてしまいますが,回転準位に関しては小分子ゆえの制約が生まれるという興味深い例です。いずれの二原子分子も,温度上昇に伴って熱容量は増加しています。これは温度上昇に伴って,エネルギーが高い振動準位への励起が徐々に増えているためです。
二酸化炭素 $\ce{CO2}$ や二硫化炭素 $\ce{CS2}$ はどちらも直線分子で,回転の自由度は二原子分子と同様ですが,原子数が増えるため振動モードの数が増え,また分子間相互作用の影響も大きくなるため,実測値は理論値から乖離します。非直線の分子は水が比較的理論値に近いですが,メタンは結合数が多いため,振動モードの数が増え,温度上昇により振動準位への励起が増えるため,熱容量の温度依存性が顕著になっています。六フッ化硫黄 $\ce{SF6}$ は重い原子同士の結合を複数持つため,振動準位間隔が小さく,室温付近でも多くの振動モードが励起されます。そのため,熱容量が非常に大きく,さらに温度上昇とともに顕著に増加します。