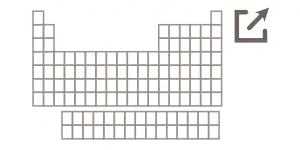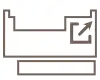$\pH$ 計算の実際(塩)
酸・塩基水溶液の $\pH$ は前節までで求められるようになりました。本節では塩の水溶液について考えます。高校の化学で強酸と弱塩基からなる塩の水溶液は酸性,弱酸と強塩基からなる塩の水溶液は塩基性と習ったものの,何故という理由あるいは具体的に $\pH$ がいくつになるかについてまでは深く考えなかった方が多いのではないでしょうか。塩を水に溶かしたときに,ただ電離して溶けただけであれば溶液のプロトンは増えも減りもしないので $\pH$ には影響がないはずです。しかし実際には電離に伴い生じたカチオンやアニオンが水と反応して溶液中のプロトン濃度を変化させるので $\pH$ は変化します。このような水溶液中で化学種が水分子と反応してプロトンの授受が起こる反応を加水分解(hydrolysis)といいます。と言っても,既に加水分解の例はたくさん見てきていて,例えばブレンステッド酸の種類で学んだようにアクア酸水溶液が酸性を示すのも加水分解ですし,アンモニア水が塩基性を示すのも加水分解によるものです。
塩の元となった酸・塩基の強弱で場合分けして考察します。
強酸と強塩基からなる塩の水溶液
強酸と強塩基からなる塩の代表例は塩化ナトリウム $\ce{NaCl}$ だと思いますので,塩化ナトリウムを水に溶かしてみます。
電離によってナトリウムイオンと塩化物イオンが生じますが,これらのイオンは(水和はしますが)加水分解はしません。つまり次式のような反応は考えなくてよいことになります。
ゆえに $\ce{NaCl}$ を水に溶かしても加水分解は起こらずプロトン濃度も変化しませんので,皆さんよくご存じの通り,強酸と強塩基からなる塩の水溶液は中性 $\pH\,7$ となります。
強酸と弱塩基からなる塩の水溶液
この組合せでは水溶液は酸性になることは知識としてあると思いますが,そのメカニズムを考察します。具体例を用いた方がイメージしやすいと思いますので,塩化アンモニウム $\ce{NH4Cl}$ を水に溶かしてみます。
上で述べたように塩化物イオンは加水分解しませんが,アンモニウムイオンは加水分解します。
二通りの書き方をしましたが形式的な違いなのでどちらで考えていただいても結構です。なぜこのようなことが起こるのか?それはアンモニアが弱塩基だからであって,$\ce{NH4OH}$ は完全電離しないため,$\ce{NH4+}$ を水に溶かすと水から $\ce{OH-}$ を引き抜いて $\ce{NH4OH}$ となり後にプロトンを残すからです。
どのくらいのプロトンが生じるでしょうか。アンモニウムイオンを水に溶かしたときのプロトンの電離度を $\alpha$ としましょう。つまり仕込みの塩濃度が $\Csalt$ のとき,加水分解で新たに生じたプロトン濃度は $\Csalt\alpha$,電離せずに残ったアンモニウムイオン濃度は $\Csalt(1-\alpha)$ となります。これをアンモニウムイオンの酸解離定数 $\Ka{}$ に入れてみます(水由来のプロトンは無視します)。
式\eqref{KaCsa}は二つの情報を含んでいます。一つは $\Ka{}$ と $\Csalt$ から $\alpha$ が求まるということ。
もう一つは式\eqref{detalpha}から求めた $\alpha$ を使ってプロトン濃度が求まるということ。
$1 \gg \alpha$ のとき,式\eqref{detH}右辺の分母は $\Csalt$ と近似できるので,プロトン濃度は次式となります。
$1.0\times 10^{-2}\unit{M}$ 塩化アンモニウム水溶液の $\pH$ を求めます。$\Ka{}=5.6\times 10^{-10}$ とします。
はじめに電離度を見積もります。
これより $1 \gg \alpha$($0.05 > \alpha$)ですので近似式が使えます。
よって $\pH\,5.63$ と求まります。電離度は濃度が低くなると大きくなります。どの程度希薄になると $\alpha = 0.05$ に近づくか逆算すると $2.12\times 10^{-7}\unit{M}$ 程度となりますので,通常は近似式\eqref{phapprox}を用いて問題ないことが分かります。
弱酸と強塩基からなる塩の水溶液
塩化アンモニウムの逆パターンです。具体例としては酢酸ナトリウム $\ce{CH3COONa}$ あたりが典型的でしょうか。水に溶かして生じるナトリウムイオンは加水分解しません。酢酸イオン $\ce{AcO-}$ による加水分解を考えます。
この反応では酢酸イオンは塩基としてはたらいていますので $\Kb{}$ を使いましょう。$\ce{AcO-}$ はプロトンを電離するのではなく水からプロトンを奪うので,電離度という言葉は馴染みません。ここでは $\ce{AcO-}$ が加水分解する割合(水からプロトンを奪う割合)と言う意味で加水分解度 $\alpha$ と呼ぶことにして,$\Kb{}$ と $\alpha$ の関係を求めます。$\alpha$ が酢酸 $\ce{AcOH}$ の電離度ではない点に注意してください。
$\Ka{}$ は $\ce{AcO-}$ の共役酸,すなわち $\ce{AcOH}$ の酸解離定数です。式\eqref{KbCsa}から $\alpha$ と $\ce{[OH-]}$ が求まります。
$1 \gg \alpha$ のとき水酸化物イオン濃度とプロトン濃度はそれぞれ次式で近似されます。
$1.0\times 10^{-2}\unit{M}$ 酢酸ナトリウム水溶液の $\pH$ を求めます。$\Ka{}=1.74\times 10^{-5}$ とします。
はじめに電離度を見積もります。$\Kb{} = \Kw/\Ka{} = 5.74\times 10^{-10}$ です。
これより $1 \gg \alpha$($0.05 > \alpha$)ですので近似式が使えます。
よって $\pH\,8.38$ と求まります。
弱酸と弱塩基からなる塩の水溶液
酢酸アンモニウム $\ce{NH4OAc}$ を水に溶かしたときの加水分解を考えます。
電離により生じるアンモニウムイオンと酢酸イオンのどちらもが加水分解に関わりますので,それぞれ別個に考えて合算すればよいと考えるかもしれませんが,式\eqref{nh4oachyd}に示したように全体としての平衡反応なので分けて考えることはできません。式\eqref{nh4oachyd}の平衡定数を書きます。加水分解反応の平衡定数なので加水分解定数 $K_\mathrm{h}$ と呼びます。$\Ka{}$ が二つ出てくるので $\Ka{}(\ce{NH4+})$ と $\Ka{}(\ce{AcOH})$ で書き分けます。
両辺から水を省くと結局アンモニウムイオンから酢酸イオンへのプロトン移動が起こっていることが分かります。一方,式\eqref{nh4oachyd}におけるプロトンの電離度(あるいは加水分解度)を $\alpha$ とすると $K_\mathrm{h}$ は次式で表されます。
以上から $\Ka{}(\ce{NH4+})$ は次式で表され,プロトン濃度と $\pH$ が求まります。
$1.0\times 10^{-2}\unit{M}$ 酢酸アンモニウム水溶液の $\pH$ を求めます。$\pKa{}(\ce{AcOH})=4.76$,$\pKa{}(\ce{NH4+})=9.25$ とします。
いきなりですが,式\eqref{phpka12}で求めます。
酢酸の $\pKa{}$ とアンモニアの $\pKb{}$ がほぼ等しいので,塩の水溶液は濃度にかからわず中性になります。
$1.0\times 10^{-2}\unit{M}$ ギ酸アンモニウム水溶液の $\pH$ を求めます。$\pKa{}(\ce{HCOOH})=3.75$,$\pKa{}(\ce{NH4+})=9.25$ とします。