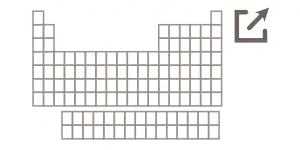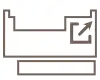リン(燐)
りん
phosphorus
リンは原子番号 $15$ の元素で,単体にはいくつかの同素体(allotrope)が存在することが知られており,正式に認められているかどうかは別として,これまでに 12 種類もの同素体が報告されています。ただし,教科書などで紹介される黄リンや赤リン,あるいは紅リンと呼ばれるものは,不純物を含んでいたり,複数の同素体の混合物であったりするので,厳密な意味ではリンの同素体ではないとする考え方もあり,その場合,白リン,紫リン,黒リンがリンの同素体の基本ということになり,これらがさらに細かく分類されます。
現在では単体のリンやリンを含む無機物は主にリン鉱石から製造されますが,リン元素の発見は鉱物からではなく,生体由来の物質からブラント(Hennig Brand)によってリンが単離されたことに端を発します(1669 年)。下の絵画を見たことがある方もいると思います。この絵はブラントがリンを発見した現場を構図にしたもので,ちょっと強調しすぎのような気はしますが,暗闇で光るというリン(正確には白リン)の性質を描き表しています。

ブラントは錬金術師でしたので,彼の本来の目的は新元素の発見ではなく,金を産み出すことにありました。上で「生体由来の物質」と書きましたが,彼は「尿には銀を金に変える力がある」と考え(まぁ黄金色ですし...),大量の尿を集めて腐食させ,それを濃縮するという実験を行っていました。もちろん錬金には成功しませんでしたが,その代わり,新元素の発見という歴史に名を残す偉業を成し遂げたわけです。いやはや,腐った尿を煮詰めるなどとは,偉人の発想というのは凡人には理解しがたいものです。現代でしたらノーベル賞とイグノーベル賞をダブル受賞すること間違いないでしょう。ブラントの後ろに暗く描かれているのはお母ちゃんと息子でしょうか。驚きの発見にワクワクを隠せないブラントの表情とは対照的に,後ろの二人はあきれ顔に見えなくもありません。この時代の実験器具は粗末なものですから,濃縮時には恐らく臭いも蒸気も漏れ出たことでしょう。
リン資源
単体のリンは天然には存在しません。しかし,生体には核酸,アデノシン三リン酸(ATP),リン脂質そして骨などとして多くのリンが含まれており,リンが尿から発見されたということからも分かるように,排泄物にはリンが含まれます。特に海鳥の糞が堆積して化石化したものはグアノ質リン鉱石といって貴重なリン資源で,かつては日本でも沖大東島で採掘が行われていましたが,今では世界中でほとんど採掘され尽くしてしまい,資源としては枯渇してしまいました。
現在の主要なリン資源は古生物が起源のリン鉱石で,日本は全量を輸入に頼っています。リン鉱石というのはリンの原料となる鉱石の総称みたいなもので,リン酸カルシウム $\ce{Ca3(PO4)2}$ が主であると紹介されることもありますが,実際にはリン灰石(りんかいせき)などのリン酸石灰岩が主要鉱物となっています。リン灰石という言葉はあまり聞いたことがないという方も,英語名のアパタイト(apatite)と言えばなんとなく聞き覚えがあるのではないでしょうか。リン灰石(apatite)の化学組成は $\ce{Ca5X(PO4)3}$ で,$\ce{X}$ には $\ce{F-}$,$\ce{Cl-}$,$\ce{OH-}$ が入り,それぞれフッ素リン灰石(fluorapatite),塩素リン灰石(chlorapatite),水酸リン灰石(hydroxyapatite)といいますが,単にリン灰石と言えば,フッ素リン灰石を意味することが一般的です。水酸リン灰石はハイドロキシアパタイト(ヒドロキシアパタイト)とも呼ばれ,歯磨き粉に配合されていて CM でもときどき見かける用語です。
アパタイトの化学組成は $\ce{Ca5F(PO4)3}$ ですが,結晶中ではこれを二倍した $\ce{Ca10F2(PO4)6}$ が一つの単位となっていますので,こちらの表記をする場合もあります。これはリン酸カルシウム $\ce{Ca3(PO4)2}$ が三つと,フッ化カルシウム $\ce{CaF2}$ が一つの比からなる複塩(double salt)と見ることもできますが,複塩というのは二種類以上の塩の成分がそのまま存在する塩のことで,溶液にしたときに元の塩の成分がそのままイオンとして生じることで,「あぁ元のままだな」と確認することができますが,アパタイトは常温・常圧では溶解度が小さいため,アパタイトを複塩と分類することは一般的ではありません。
虫歯予防のために歯医者でフッ素を塗布してもらったり,フッ素入りの歯磨き粉を用いたりすることがあります。この場合のフッ素とはもちろん $\ce{F2}$ のことではなく,フッ化物イオン $\ce{F-}$ のことを言うのですが,ハイドロキシアパタイトよりも,$\ce{OH-}$ を $\ce{F-}$ で置換したフルオロアパタイトの方が酸に対する耐性が強いので,歯の表面をフルオロアパタイトに変換することで虫歯を防ぐというのが使用の根拠となっています。
製造
主たるリン鉱石はリン酸カルシウムではなく,リン灰石であると上で述べましたが,単体のリンの製造に関わる反応を考える限りにおいては,リン酸カルシウムの反応を考えることで説明ができ,以下の化学式に集約することができます。
この反応は,リン鉱石にケイ砂とコークスを加えて$1300$~$1400\oC$くらいで加熱することにより起こります。
鉄の製錬では,鉄鉱石にコークスと石灰石(炭酸カルシウム)を加え,高炉で溶かして銑鉄を得ます。この場合の石灰石の役割は,カルシウムイオンが鉄鉱石中の不純物である $\ce{SiO2}$ と反応してスラグ(slag)として取り除かれることにありますが,リン鉱石の場合はカルシウムがすでに含まれていますので,ケイ砂 $\ce{SiO2}$ を意図的に加えることで,スラグとしてカルシウムを除くわけです。これにより生じたリンの酸化物はコークスで還元され,単体リンの蒸気となり,これを冷却すると黄リン(白リン)が得られます。
白リンは,四つのリン原子が正四面体の各頂点を占めるような構造を持つ分子性の物質 $\ce{P4}$ であることが白リンのベンゼン溶液の凝固点降下や $\ce{CS2}$ 溶液の沸点上昇からも確認されています。よって,もしその事実を明確にするのであれば,上の化学式を2倍して次のように書くのが正しいとも言えます。
一方,蒸留により得られる冷却前の気体のリンは,$800\oC$ くらいまでは $\ce{P4}$ として存在するのですが,この温度を超えると $\ce{P2}$ の成分が増えてくることも分かっていますので,その意味では $\ce{2P}$ と書くスタイルの方が適切かもしれません。
上で述べたように,黄リンは厳密にはリンの同素体ではなく,不純物を含む白リンであると考えられていますが,日本語の教科書ではリンの同素体として黄リンと書いてあることがまだまだ多いようです。一方,英語の教科書を見ると yellow phosphorus の表記はなく,white phosphorus とだけ書かれたものが目立ち,扱いを比べると,日本では単体リンについての認識がやや遅れているように感じます。
白リンは化学的に活性で,発火点が $34\oC$ ですので,空気中で自然発火します。$34\oC$ であれば,涼しい部屋で扱えば大丈夫と思うかもしれませんが,実際は空気中の酸素と反応して発熱しますので,自然と $34\oC$ に達して発火します。したがって白リン(黄リン)は水中で保存するのが基本となります。黄リンは現在日本では製造されていません。面白いことに,リンの単体で毒性が認められるのは白リン(黄リン)だけで,その他のリンの形態には顕著な毒性はないと考えられています。これは重金属などの元素そのものが有害であるという毒性とは異なる特徴です。生体内に多く含まれることからも分かるように,リン元素そのものには強い毒性はなく,白リンの化学的特徴,すなわち正四面体構造をとることにより大きく歪んだ化学結合が白リンの化学活性を高めた結果,毒性を生じさせているものと考えられます。
赤リン(red phosphorus)は,白リンを酸素に触れないようにして $200\oC$ くらいに加熱することで得られます。白リンが分子性の物質 $\ce{P4}$ であるのに対し,赤リンは無定形固体であるため,赤リン分子というものは存在しません。白リンの四面体が開裂して重合して連なったものと考えれば良いでしょう。このことを $\ce{P_\infty}$ と表現することもあります。黄リンを目にする機会はほとんどない一方,赤リンはマッチや花火などに使われていますので,身近な存在と言えます。
白リンをビスマスの存在下で封管して加熱すると紫リン(violet phosphorus)が得られます。一方,白リンを加圧下で加熱すると(あるいは十分に加圧すれば室温で)金属光沢を有する黒リン(black phosphorus)が生成します。黒リンはリンの同素体の中では熱力学的に最も安定なものです。熱力学では,指定温度において,$1\unit{bar}$ で最も安定な状態にある元素の単体を,その元素の基準状態(reference state)といい,基準状態にある単体の標準生成エンタルピーをゼロと約束します。例えば室温であれば,炭素の基準状態はダイヤモンドではなく,熱力学的により安定なグラファイトということになるので,ダイヤモンドは単体ですが,その標準生成エンタルピーはゼロではありません。しかし,リンの場合は例外で,最も安定な黒リンを基準状態にするのではなく,最安定ではないが実験的に再現性が良い白リンをリンの基準状態とすることが約束されています。
リンの利用
リンは肥料としての利用が重要で,上述のように日本はリン鉱石のすべてを輸入に頼っていますので,リン資源の確保は国の農業を左右する重大事項です。また,肥料に限らず,多くの工業製品でリンを含む物質が利用されており,その範囲は燃料電池の電解質から食品添加物や医薬品に至るまで広く,また農薬や殺虫剤のような薬品にもリンが含まれるものがあります。
ここでは昔からの利用の一つとして,マッチについて触れておきます。現代ではマッチも過去のものとなりつつありますが,それでも軽くて安くてコンパクトなマッチは,着火源として今でも有用です。私たちが目にする下の写真のようなマッチは安全マッチと呼ばれる赤リンを利用したもので,1855 年頃に発明されたものです。
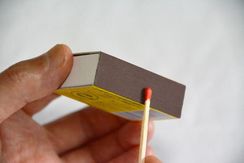
安全マッチの発明までは,1826 年に発明された黄リンを用いた黄リンマッチが用いられていて,マッチ売りの少女が売っていたマッチも,この童話の初出が安全マッチが発明される前の 1845 年であることを考えると,黄リンマッチであったものと思われます。黄リンマッチの特徴は,どこで擦っても発火するという点で,便利な反面,持ち運びなどで勝手に発火しますし,黄リンの毒性による事故も多発しました。そこで自然発火せず,毒性の心配もない赤リンを利用した安全マッチが開発され,現在のマッチの原型となりました。黄リンマッチは日本では 1919 年に使用が禁止されています。
マッチとマッチ箱の写真が上にありますが,赤リンはどこに使われているかご存じですか?なんとなくマッチ棒の先端に塗られている頭薬に赤リンが含まれているような気がしますが,実はそうではなく,赤リンはマッチ箱の側面のマッチを擦る場所(側薬)に使われています。頭薬として塗られているのは燃焼を継続させるための塩素酸カリウム $\ce{KClO3}$ や硫黄などで,赤リンが活躍するのはシュッとマッチを擦って発火させる初めだけです。むしろ側薬の赤リンが燃え続けてしまっては困るので,側薬には燃焼が継続しないように硫化アンチモン $\ce{Sb2S3}$ が含まれています。
火のないところに煙は立たずと言いますが,マッチの側薬を剥がして灰皿で燃やすとタール状の物質が残ります。これを指先につけて擦り合わせると,あら不思議,火のないところから煙が出てきます。リンの酸化物が指先の水分と反応して煙(のようなもの)が生成するようです。昔は子供の遊びとしてよく知られていて,私も何度も試した思い出がありますが,時代は変わりましたので,お試しの際はくれぐれも自己責任(保護者の方とご一緒に)でお願いします。
最終更新日 2023/02/12