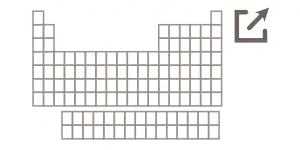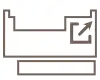熱力学第 0 法則
熱力学では,経験上,現実の世界を正しく表しているだろうと考えられるいくつかの事項を証明なしに公理として受け入れ,それらを第ゼロから第三の四つの法則としてまとめ,これらを基盤として理論を構築しています。これらは「経験的に」正しいと受け入れているだけです。よって,もし熱力学の公理が実は正しくなかったと判明してしまうと,理論の屋台骨がぐらつきます。しかし,現状で公理に対する反例は見つかっていませんし,仮に将来見つかったとしても,考える問題に対して公理が十分に成り立つのであれば,熱力学を適用できますので,熱力学が価値を失うことはありません。化学熱力学の範疇ではまぁ大丈夫でしょう。よって,本講義では安心して四つの法則を受け入れることにします。
熱力学第 0 法則は次のように定められます。
系 1 と系 2 が熱平衡状態にあり,系 2 と系 3 がやはり熱平衡状態にあるとき,系 1 と系 3 は熱平衡状態にある。
そもそも,なぜ第 1 から始めずに第 0 からなのでしょうか。これは,第 0 法則で述べていることがあまりに基本的で当たり前すぎたため,最初は法則として定めていなかったのですが,他の法則が定まってから改めて「やっぱりこれも法則として定めておく必要がありますね。しかも極めて基本的なことなので最初に置きたいですね」ということで,第 0 の称号が与えられたというのが成り行きのようです。
では第 0 法則はどこが当たり前すぎるのでしょうか。そして,もし第 0 法則を認めない立場をとったならば,どのような不都合が生じるのでしょうか。第 0 法則は雑に言うと「系 1 と系 2 の温度が同じで,かつ系 2 と系 3 の温度が同じならば,系 1 と系 3 の温度も同じである」ということを述べています。つまり第 0 法則を認めないということは,「系 1 と系 2 の温度が同じで,かつ系 2 と系 3 の温度が同じであっても,系 1 と系 3 の温度が異なることがある」ということになります。これはあまりにも私たちの経験と符合しませんし,もし認めてしまうと温度というものの意味がなくなります。だから第 0 法則は公理として証明なしに受け入れることになりました。
第 0 法則を受け入れることで得られるメリットは,温度計が使えるようになるということです。上の系 2 が温度計であるとします。系 1 に温度計を接触させ熱平衡状態になったとき,温度計が $50\oC$ を示したとします。その後,温度計と系 3 を接触させて熱平衡状態になったとき,やはり温度計が $50\oC$ を示したとします。このとき,第 0 法則により,系 1 と系 3 はどちらも $50\oC$ で互いに熱平衡な状態です。よって,もし系 1 と系 3 を熱的に接触させたとしても,どちらの系も巨視的な時間変化をしないということが,実際に系を接触させて確かめてみることなくわかります。
第 0 法則の存在により,温度という概念が意味を持ち,複数の系を比較して「温度が同じ」という尺度で系を分類することができるようになります。
温度計についてもう少し考えてみましょう。温度計に使われるアルコールや水銀などの液体は,分子(原子)の無秩序な運動の激しさが増すと体積が増加する性質があるので,液体の体積 $V$ を粒子の無秩序な動きの指標とすることができます。そこで,アルコールや水銀などを測定したい系 1 に接触させて,熱平衡状態になるまで待ち,そのときの $V$ から用いたアルコールや水銀の無秩序な動きの程度を数値化し,それを温度と定義すればよいのです。このとき,実際に見ているのは温度計の中の物質の温度ですが,第 0 法則により,それはすなわち系 1 の温度であるとみなして構わないわけです。数値化には基準が必要ですので,例えば $1\unit{atm}$ における水の凝固点と沸点をそれぞれ $0\oC$ と $100\oC$ に定めて,その間を等間隔に 100 分割すればセルシウス温度目盛りの出来上がりです。しかし,注意しなくてはいけないのは,必ずしも $V$ の変化は水の凝固点と沸点の間で線形に変化しないのと,アルコールや水銀といった物質の違いによっても $V$ の変化のしかたは僅かに異なるという点です。結果として,アルコール温度計が示す $20\oC$ と水銀温度計が示す $20\oC$ は厳密には同じではありません。厳密に同じになるのは基準とした $0\oC$ と $100\oC$ の 2 点のみです。また,アルコール温度計が示す $20\oC$ と $21\oC$ の温度差に相当するエネルギー差と,$50\oC$ と $51\oC$ の温度差に相当するエネルギー差は厳密には一致しません。このような,物質に依存するような方法で定めた温度のことを経験的温度(practical temperature)と言います。後に学習するように,物質に依存しない温度を定義することも可能で,こちらは熱力学的温度(thermodynamic temperature)と呼んで経験的温度と区別しています。