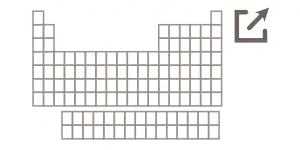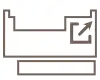微分
区間 $I$ で定義された $x$ を変数とする 1 変数関数 $y=f(x)$ を考えます。$f(x)$ の区間 $I$ 上の点 $c$ において,次の極限値が存在するとき,$f(x)$ は $x=c$ で微分可能と言います。
この極限値は微係数(または微分係数)と言います。微係数を表すには $f'(a)$ のようにプライム $'$ をつけて表すほか,$\left.\dfrac{\diff f}{\diff x}\right|_{x=c}$ のような書き方もあります。グラフで視覚的に考えると,式\eqref{difp}は分母が $x$ 軸上の変化量,分子がそのときの $f(x)$ の変化量ですので,区間 $[c, c+h]$ における $f(x)$ の平均変化率です。この区間を限りなくゼロに近づけていくということですから,$f(x)$ のグラフを描いたときの 点 $(c,f(c))$ における接線の傾きが式\eqref{difp}ということになります。
式\eqref{difp}の極限値が存在しない場合は微分可能ではありません。例えば,$f(x) = |x|$ という関数のグラフは $x=0$ で折れ曲がっているので,$h\rightarrow 0$ としたときに式\eqref{difp}の極限値が定まりません($x<0$ での接線の傾きは $-1$,$x>0$ では $+1$,$x=0$ では定まりません)。よって $f(x) = |x|$ は $x=0$ において(連続ではありますが)微分可能ではありません。連続であっても微分可能とは限りませんが,微分可能であれば連続です。
式\eqref{difp}では $h\rightarrow 0$ と書きましたが,$h$ を左(すなわち負側)から $0$ に近づけるのか,右(正側)から $0$ に近づけるのかで違った結果となることがあります。この近づけ方の違いを $h\rightarrow -0$,$h\rightarrow +0$ で区別するならば以下の 2 通りの極限が考えられます。
負側から近づけたときに極限値が存在する場合は左側微分可能,右側から近づけたときに極限値が存在する場合は右側微分可能であり,それぞれの極限値を左側微係数,右側微係数といいます。関数 $f(x)$ が点 $c$ で微分可能であるとは,$c$ における左側微係数と右側微係数が一致することと同値です。上の $f(x) = |x|$ は $x=0$ において左側微係数が $-1$,右側微係数が $+1$ と一致しないため,微分可能ではないということになります。
関数 $y=f(x)$ が区間 $I$ のすべての点で微分可能であるとき,$y=f(x)$ は(どこか 1 点ではなく)区間 $I$ で微分可能といい,微係数を与える関数を導関数といって $f'(x)$,$\dfrac{\diff y}{\diff x}$,$\dfrac{\diff f}{\diff x}$ などと表記します。区間で連続であっても,いたるところで微分可能ではない関数というものもあって,ワイエルシュトラス関数(Wikipedia)が例として知られています。
化学や物理の考察では定義された区間の全体で微分可能(よって連続)であることを前提として議論を進めてしまう場合も多いのですが,微分可能ではない状況も起こり得るので,おや?っと思ったら原理原則に立ち返ることも大切です。
導関数の公式
いろいろな関数の導関数を公式としてまとめます。微分演算には線形性があるので,以下公式で挙げた関数を定数倍,線形結合した式についても以下の公式の組合せにより導関数が求まります。$\alpha$ は任意の実数,$a$ は $1$ を除く正の実数(対数が定義できる範囲)とします。逆三角関数の場合は定義域に注意が必要です(下の逆関数の微分を参照)。
積の微分と商の微分
導関数の基本公式に加えて,複数の関数が掛け算や割り算の形で現れる場合には,積や商に関する微分公式が必要になります。二つの関数 $u(x)$,$v(x)$ を使って,積や商の形で表された関数の微分 $(uv)'$ と $\left(\dfrac{u}{v}\right)'$ は以下の公式で求められます。
積の微分の例として,関数 $f(x) = x^2 \sin x$ の導関数を求めます。$u(x) = x^2$,$v(x) = \sin x$ とおくと導関数は次式で求まります。
商の微分の例として,関数 $f(x) = \dfrac{\ln x}{x}$ の導関数を求めます($x > 0$)。$u(x) = \ln x$,$v(x) = x$ とおくと導関数は次式で求まります。
合成関数の微分
ある関数のアウトプットが別の関数のインプットになるような関数を合成関数といいます。$g$ の中に $f$ が入っている $g(f(x))$ のことで,$(g\circ f)(x)$ と書かれます。一般に $(f\circ g)(x)$ とは一致しませんので注意が必要です。関数 $y = f(x)$ があるとき,合成関数 $z = (g\circ f)(x)$,すなわち $z = g(y)$ の導関数は連鎖率により求まります。
式\eqref{pt1}と式\eqref{pt2}は表現方法を変えただけで同じことを表しています。$f(x)$ をひとかたまりとして(ひとつの変数であるかのように)$g$ を微分したものと,$f(x)$ を単独で微分したものの積をとるということです。実際には,それぞれの関数の定義された区間上で微分可能であるという条件が必要になります。
例えば,$f(x)=\sin(x^2)$ という関数を $x$ で微分するならば,$x^2$ という関数がサイン関数に埋め込まれているので,$x^2$ をひとかたまりとみなしてサイン関数を微分した $\cos(x^2)$ と,$x^2$ 自身を微分した $2x$ の積が $f(x)$ の導関数となります。
逆関数の微分
ある関数 $y=f(x)$ があるとき,これは $x$ が分かれば $y$ が一つに定まるという意味ですが,逆に $y$ が与えられたときに $x$ が一つに定まる関数を $f(x)$ の逆関数といい,$x = f^{-1}(y)$ で表します。グラフでイメージするのであれば,関数は横軸の値を決めたら縦軸の値が決まる,逆関数は最初に縦軸の値を決めたら,横軸の値が決まるということです。逆関数は単調増加(または単調減少)な関数でなければ定義できない点に注意が必要です。例えば $y=x^2$ の放物線をイメージすれば分かるように,$y$ が仮に $y = 4$ と分かったとしても $x$ が $+2$ なのか $-2$ なのかは定まりません。関数はインプットに対してアウトプットが一意に定まらなくてはいけないので,この場合は逆関数は定義できません。定義域を $x\geq 0$ のように限定すれば逆関数が定義できます。
関数 $y=f(x)$ が区間 $I$ で単調で微分可能であり,かつ $I$ 上のすべての点で $f'(x) \neq 0$ であるとき,その逆関数 $x = f^{-1}(y)$ の導関数は以下で求まります。
式\eqref{pt3}と式\eqref{pt4}は表現方法を変えただけで同じことを表しています。
例えば区間 $\left[-\dfrac{\pi}{2} \leq x \leq \dfrac{\pi}{2}\right]$ で $y = \sin x$ が定義されているとき,その逆関数 $x = \sin^{-1}y$ の微分は以下のように求まります。
上記の $(\sin^{-1} x)'$ の公式が求まりました。