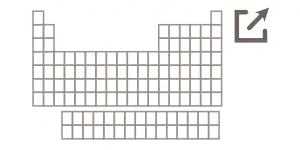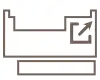強い結晶場と弱い結晶場
これまでは,エネルギーが分裂した空の $\ao{d}$ 軌道を用意して,そこに必要な数だけ電子を詰めるという方法で電子配置を考えてきました。しかし錯体の電子状態を考える上で無視できない,もう一つの重要な要素があり,それは電子間のクーロン相互作用による反発です。これは言い換えると,たとえ同じエネルギーの $\ao{d}$ 軌道に電子がトータルで同じ数だけ入ったとしても,その入り方によって電子間の反発が異なるため,出来上がる状態のエネルギーが異なることがあるということです。高スピンと低スピンを考える際に電子間反発 $P$ を導入しました。しかし,スピン状態を考えるときに限らず,たとえ同じスピン状態であったとしても,どの軌道に電子が入るかによって状態のエネルギーは異なりますし,$P$ と一括りに考えてきたものも,細かく見れば一つではありません。スピン状態によっても異なります。例えば $\ao{d}^2$ の電子配置を考えるとき,軌道のエネルギーだけを考えるのであれば,両方の電子が $\irrep{t}{2g}$ 軌道に入った状態,一つが $\irrep{e}{g}$ 軌道に励起された状態,二つとも $\irrep{e}{g}$ 軌道に励起された状態の三つの状態が考えられますが,詳しく電子の詰め方を考えると,5 個の軌道に 2 種類のスピンが組み合わさって入るので,実質的には 10 個の箱に 2 個の粒子を収めることに相当し,その組合せとして $_{10}C_2 = 45$ 通りの詰め方のパターンがあることになります。$\ao{d}^5$ であれば $_{10}C_5 = 252$ 通りもあります。これらすべてが異なるエネルギーの状態となるというわけではなく,いくつかのグループに分かれるのですが,今ここで大事なことは,電子間の反発は錯体だから生じるのではなくて,配位子が結合していない金属イオンの段階で既に存在するということ,そしてその反発によるエネルギーの大きさが,特に $\ao{3d}$ 遷移金属錯体においては結晶場(配位子場)による分裂エネルギーと拮抗しているということです。
したがって $\ao{d}^2$ 以上の場合では,結晶場分裂と電子間反発のどちらか片方を無視するわけにはいきませんし,どちらがより重要であるのかは金属イオンや配位子の種類によるので,定まっていないという(やっかいな)状況が生じます。この状況に対処する方法が考えられており,基本方針としてはより重要な(エネルギーが大きく変化する)方を先に適用し,その後に他方を考慮します。
例えば,電子間反発に比べて,結晶場分裂が大きい場合,まずは $\ao{d}$ 軌道を分裂させて,そこに必要な数だけ電子を詰めてしまいます。そしてその後で,各軌道に入った電子間の反発を考えます。これを強い結晶場の方法(strong crystal field scheme)といいます。前節までは高スピン,低スピンの考察以外では電子間反発は考えずに,分裂した $\ao{d}$ 軌道に電子を配置してきましたので,実は強い結晶場の方法に一歩踏み出していたことになります。この後,電子間反発を考慮するとどうなるのかということの求め方自体は基礎の範囲を超えますのでここでは扱いませんが,結果は後で学ぶ田辺・菅野ダイヤグラムとして表されます。
一方,電子間反発が結晶場分裂と比べて優勢である状況では,はじめにフリーの金属イオンの電子状態(原子項,atomic term)を求めておき,この原子項が結晶場によってどのような影響を受けるかというアプローチをとります。これを弱い結晶場の方法(weak crystal field scheme)といいます。結晶場によって分裂するのが $\ao{d}$ 軌道ではなくて原子項であるという点がこれまでの考え方と違っていて重要です。
強い結晶場の方法と弱い結晶場の方法というのは,結晶場分裂と電子間反発の大小関係に関する言わば両極端な状況であり,実際の錯体はこれらの中間的な状態をとる場合が通常ですが,いずれにせよ,電子間反発の効果は錯体の吸収スペクトルにその影響が現れますので,錯体の電子状態を考えるうえで非常に重要なものと言えます。事例については後の節で紹介します。