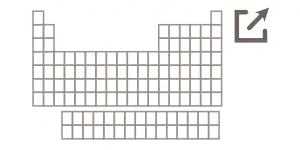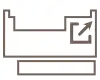フロギストン
ふろぎすとん
phlogiston
フロギストン説(phlogiston theory)という言葉を聞いたことがあるでしょうか。17 世紀の終わりから 18 世紀にかけての科学者を惑わせた,いわくつきの化学理論とでも言うべき存在です。フロギストン説の主役であるフロギストン(phlogiston)は,燃焼を理解する本丸として,かつて科学者に広く受け入れられたのですが,ではフロギストンとはいったい何でしょうか。
フロギストンは物質元素のひとつと考えられていました。
そのように言われると「周期表にそんな元素あったかな?」となりますが,表記の過去形に注意してください。私たちが普段用いる元素周期表にフロギストンは載っていません。実はフロギストンは現在私たちが知っている化学元素ではなく,ベッヒャー(J. Becher)の理論を原型とし,弟子のシュタール(G. Stahl)が 1697 年の著作をベースに確立したフロギストン説(phlogiston theory)に登場する,燃焼にかかわる元素です。ただし,フロギストンという言葉そのものは,燃焼をつかさどる何かしらのものとしてシュタールよりも前から使われていたようですので,シュタールはフロギストンを見出したというよりは,フロギストンに対して,元素という特性を解釈として与えたと考えるのがよさそうです。phlogiston の語源は炎を意味するギリシア語の phlox です。
現代の私たちが燃焼にかかわる元素と聞くと,酸素を真っ先に思い浮かべます。また,一般的な燃焼が酸化反応の一形態であり,炎の実体は光と熱であって物質ではないことを私たちは知っています。しかし,プリーストリー(J. Priestley)による酸素の発見は 1774 年ですので,フロギストン説が提唱された当時,酸素の存在は知られていません。もちろんフロギストン説は現在では否定されているのですが,酸素というものを知らない,あるいは元素というものの概念が確立していないという前提で考えると,フロギストンという(今となっては)架空の元素によって物質の燃焼を説明するフロギストン説はなかなかの説得力を持っています。当時の多くの科学者はフロギストンの存在を信じ切っており,実験的な矛盾が見つかったとしても,フロギストンの存在を疑うのではなく,フロギストンの性質を見直す(解釈しなおす)ことによって乗り切り,提唱から 100 年ほどの間,フロギストン説は正しい理論として受け入れられてきました。実は酸素を発見したプリーストリーもフロギストン肯定派で,酸素の発見によってフロギストンを否定したのかと思いきや,自分が発見したもの(今日の酸素)は,フロギストンが抜けた空気であると,フロギストン説に基づいて自分の発見を解釈しています。
フロギストン説に基づく燃焼の解釈
私たちは「可燃物が燃えると灰になる」と考えるのが一般的だと思いますが,フロギストン説では考え方が逆転して「可燃物は灰とフロギストンからできている」と,灰ありきの立場をとります。そして燃焼に対しては「灰とフロギストンの結合体である可燃物からフロギストンが抜けると,後に灰が残る」と解釈します。もう少し具体的に考えるのであれば,例えば木は木灰とフロギストンからできており,木が燃えるとフロギストンが抜けてなくなり,あとに灰が残るというわけです。もちろん灰が軽いのはフロギストンが空気中に逃げてしまったためです。フロギストンがなくなると木は燃え尽きて燃焼はとまります。
空気が受け入れられるフロギストンの量には限界があって,空気がフロギストンで飽和すると,フロギストン空気というものになり,その中では燃焼は起こりません。上で述べたプリーストリーが酸素を発見した際,彼はこれを空気からフロギストンが抜けたもの(脱フロギストン空気)であると考え,それゆえものが激しく燃えるのだと解釈しました。
こう書くと,当然「それでは金属の燃焼はどう説明するのか。燃焼により質量が増加するではないか」と反論を受けます。しかし,フロギストン説が提唱された当時,まだ科学に定量性という概念は定着しておらず,鉄が燃えて重くなるという事実よりは,鉄の燃えカスを石炭で焼くと,フロギストンが石炭から鉄の燃えカスに移り,金属の鉄が得られるという考え方こそが重要視されました。それでも質量の増加は事実としてあるわけで,それを説明するために,フロギストンが抜けると金属が濃縮されて重くなるだとか,熱の一部が金属に付着して重くなるだとか,果てはフロギストンは負の質量をもっているだとか,現代の目で見るとトンデモ系の理由を後付けして批判をかわしていました。
フロギストン説の否定
誰がフロギストン説にとどめを刺したのか。ラボアジエ(Lavoisier)と考えるのが通説です。彼の強みは定量性を化学に取り入れたことです。定量性というのは数字で考えるということです。例えば,実験して質量が増えたという現象だけを見ている場合は定性的に考えているということになります。一方,質量がどのくらい増えて,その増えた量を矛盾なく合理的に説明するにはどのような仮説を立てる必要があるか,あるいは既にある仮説は具体的に増えた量を説明するのに矛盾がないかといった考え方を進めていくのが定量的に考えるということです。ラボアジエは,化学反応の前後で物質の総質量は変化しないとする質量保存の法則を 1774 年に見出し,同年に燃焼が酸素との結合であることを見抜きました(プリーストリーによる酸素の発見と同年です)。また 1789 年にはフロギストン説を批判する論文を出版しました。内容は,つじつまを合わせるためのフロギストンの奇々怪々な性質(を主張する人々)に対して「いいかげんにしろ!」と今でいうところの「ブチ切れた」論文といったところです。定量的な自身の実験結果に自信を持っていたのでしょう。この論文に対しては賛否両論の大議論が巻き起こりますが,次第に彼の説は受け入れられ,それがプルーストの定比例の法則(1799 年),ドルトンの原子論(1801 年),アボガドロの分子仮説(1811 年)という近代化学の発展へとつながっていくわけです。
フロギストン説の背景
フロギストン説が登場する背景として,17 世紀の当時,まだ人類は現代の私たちが考えるような,物質を構成する粒子である原子という考えには行き着いていませんでした。と言っても,世界は自然の最小単位からできているとする,原始的な原子論の考えは,実はデモクリトス(Democritus)が大成し,エピクロス(Epikouros)が継承した紀元前の古代ギリシア哲学の中にすでにあったのですが,それよりもアリストテレス(Aristotle)が考える四元素説といって,すべては「火,空気,水,土」からなるとする世界観が広く受け入れられており,また,四元素説を含むアリストテレスによる哲学は,アリストテレス主義として権威を持っていました。科学と権威は別物と頭ではわかっている現代の私たちでさえ,両者を完全に分離することが難しいのですから,当時,教会とも深く結びついたアリストテレス学派を批判することがいかに大変であったかは想像に難くありません。ガリレオによる地動説もその一例です。
アリストテレス主義が科学の進展に(今から思えばネガティブな)影響を与えた期間,なんと 2000 年以上。アリストテレスはさまざまな学問の礎を築いた人物であることも事実ですので,このことのみをもって,もしアリストテレスがいなければ科学が 2000 年早く進んだということにはもちろんならないのですが,人類というものは一度真実と思い込んでしまうと,そこからの脱却がいかに難しいかということがわかる良い例ではないでしょうか。
しかしながら,17 世紀も半ばを過ぎた頃からアリストテレス主義に対する懐疑的な見方が出始め,権威を鵜呑みにするのではなく,事実から演繹(論理的に推論)する方法論が受け入れられるようになります。これは今では当たり前のようですが,それまではアリストテレスによる不動の結論ありきで,その結論にたどり着くように論じるのが学問であったのが,入口と出口がひっくり返ったわけですから大転換です。要は詭弁だったわけですが,プロセスそのものは論理的であったため厄介だったのがアリストテレス主義だったわけです。今でもこのような論じ方をする人がいるような,いないような...
このような時代背景のもと,物質の理解についても,物質を分解してたどり着く究極の粒子からすべてができているという考え方が少しずつ広がり始めます。例えばボイルの法則(気体の体積と圧力は反比例する)で知られるボイル(R. Boyle)は粒子論者であり,1661 年に出版した懐疑的化学者(The Sceptical Chymist)にて四元素説を批判しています。
この粒子論の高まりが起こった時期に登場し,ラボアジエによる化学元素の提唱(1789 年)やドルトン(J. Dalton)の原子説(1801 年)という近代化学の幕開けの時期に至る約 100 年間をつないだ化学理論がフロギストン説だったわけです。
フロギストンという考え方は結果的には間違っていたわけで,その点だけを見るとやはり間違いである四元素説と変わりないと見えてしまうかもしれません。しかし一方で,錬金術を含む近代以前の(原始的な)化学は経験の積み重ねでできており,物質を理解する合理的な統一的理論というものは存在しませんでした。その意味ではフロギストン説は,観察結果に基づき一貫した理論体系の下で物質を理解しようとした初めての試みということもできます。方法論という意味では,現代にまでつながるその後の近代化学のさきがけにもなったわけですから,この 100 年がまったくの時間の無駄ということではなかったように思われます。フロギストンを最後まで肯定し続けたプリーストリーが酸素の発見者(彼は脱フロギストン空気と呼んだわけですが)として,あるいは水素を発見して,これこそがフロギストンであると考えたキャベンディッシュが高校の教科書に名前が載ることはあっても,フロギストン説を提唱したシュタールの名前を見ることがないのは少々残念な気もします。
フロギストン説の説明を読んで「そんなバカな」と思った方,もしかしたら 18 世紀の科学者と同じ体験をしているのかもしれません。当時の科学者はフロギストンを信じており,ラボアジエの説を聞いて「そんなバカな」と感じたわけです。現代の原子論を信じている私たちがフロギストン説に対して「そんなバカな」と思ったとき,それは本当に事実と,事実をもとにして自分で演繹して得られた「バカな」という結論でしょうか。「教科書に載っているから」「先生が言っているから」「ネットに書いているから」が理由であるならば,それはフロギストン説を信じていた人たちと何ら違いがないことになってしまいます。もちろんすべてを自分で構築することなどできません。しかし,できないからこそ,自分の常識に反することを安易に「バカな」で片付けてしまうことは危険なのではないでしょうか。科学的に考えるとはどういうことか,そういったことまで考えさせてくれるのがフロギストン説の歴史的価値であるように思います。
参考
- 現代化学史 原子・分子の科学の発展,廣田襄, 京都大学出版会
- The Sceptical Chymist, Robert Boyle
最終更新日 2025/06/26